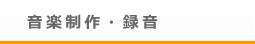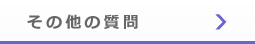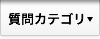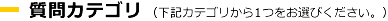切実なお悩みですね。
確かにテレビ等で歌モノの後ろで弦四が弾いている風景を見かけます。
結論から言いますと、「打ち込み」と「生」では、表現力や情報量が段違いに違います。
この差は、編成が小さくなるほど顕著になる(と感じています)ので、
6422などの複数編成より、各パート一本の弦楽四重奏の方がより差を感じると思います。
現在、PC音源の進歩は目覚ましく、大変リアルな弦楽の音源が各社から発売されていますが、
やはり小編成になるほど「生」との差を感じざるえない傾向にあるといえるでしょう。
打ち込みで弦をリアル聴かせたいならば、やはりソロ音源より「群」の音色を使う方が有利でしょう。
(もしくは両者を上手くブレンドするとか・・)
現時点では、アレンジや打ち込みのテクニックでは超えられない壁は確かにあると感じています。
1度「生楽器」で弾いて貰うチャンスがあると良いですね。
「生」と「打ち込み」その違いを肌で感じる事ができるでしょう。
Q 歌モノのストリングスアレンジについて

いっさー
(いっさー)
2020.10.25 作曲・編曲 ★0.0

普段歌モノのストリングスアレンジをする際、
音色は「Strings」や各パートに別れた音色を選ぶ場合でも、
「Violins」や「Cellos」のように、複数人での演奏をサンプルした音色を選んでおり、
いわゆる合奏でアレンジしています。
しかし、テレビの歌番組やライブ映像をみると、
意外と4人の重奏のスタイルが多く、
レコーディングでも予算の関係もあり、
4重奏で録音するケースが多いと聞いたことがあります。
しかし、ソロ音色でアレンジをすると、
どうしても4リズムに存在感で負けてしまったり、
音量を大きくしないと、ストリングスが登場している効果を
感じられません。
ユニゾンにすると、割と存在感がでますが、
4声に振り分けると、
どうしても上記の問題に当たります。
しかし、実際に上に挙げた様な媒体で流れるストリングスは、
存在感のなさは感じませんし、
4人でも十分に聞こえます。
私はVienna Instruments を使用していますが、
生演奏と打ち込みの違いは大きいでしょうか?
もしくはアレンジの技術的な問題なのか、、
結構悩んでいます。